こんにちは。「自由.online」ブログ編集部です。
今日は子育て世代の皆さんにとって嬉しいニュースを詳しく解説します。
政府は「出産費用の無償化」を本格的に進めています。
この記事では、
- 政府発表の概要
- 経済学的観点から見たメリットとデメリット
- 今後の注目ポイント
をわかりやすくまとめました。
これから出産を考えている方も、制度の動向に興味がある方もぜひ最後まで読んでくださいね。
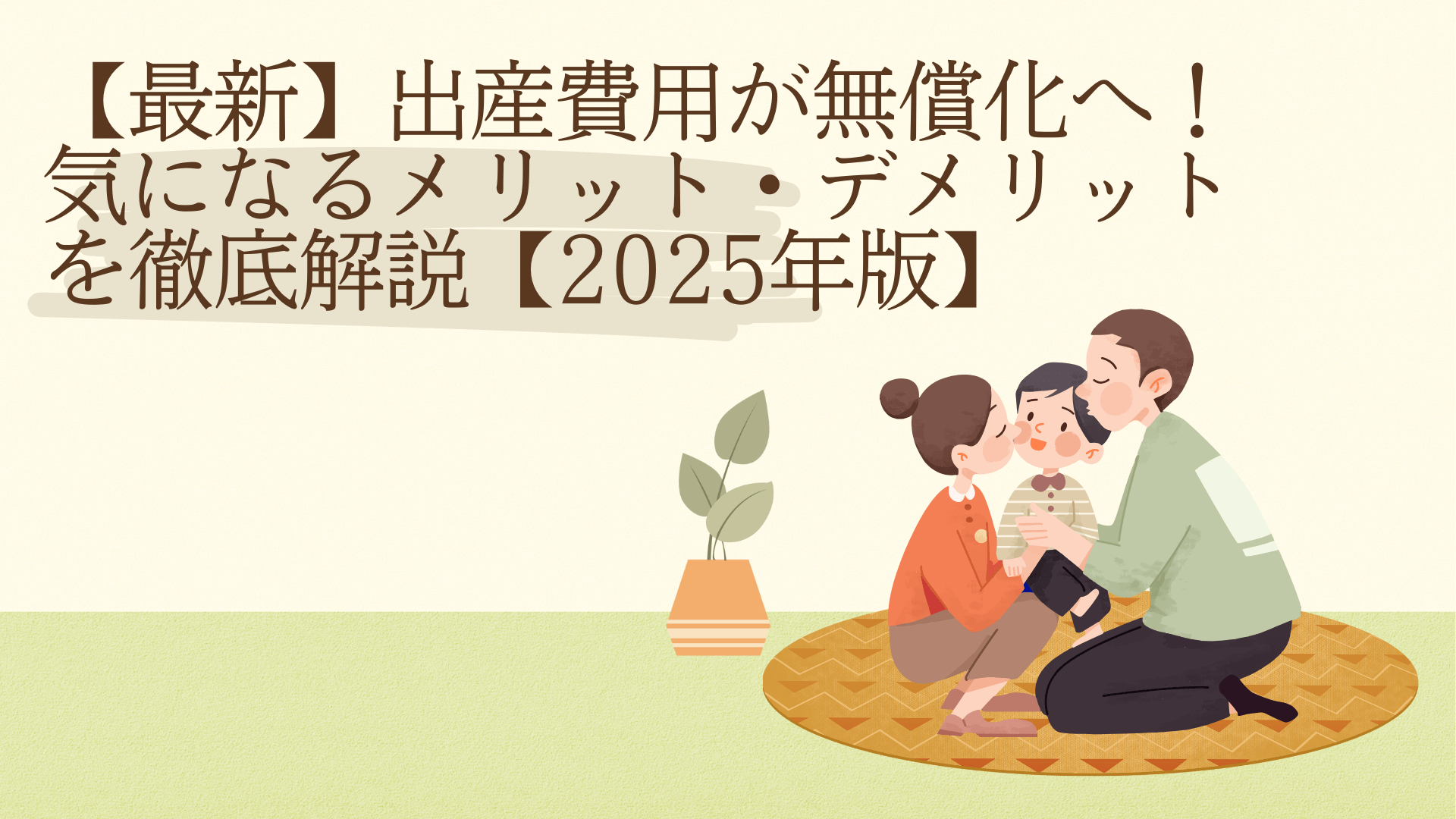
そもそも「出産費用無償化」ってどういうこと?
現在、日本では「正常分娩」は公的医療保険の対象外。
出産育児一時金(2023年4月から 50万円 に増額)を使っても、多くの家庭が 数万〜十数万円 の自己負担をしています。
しかも地域差が大きく、
東京都:平均約60万5,000円
熊本県:平均約36万1,000円
と20万円以上の開きがあるのが現状です。
そこで政府は、
「出産費用そのものを医療保険でカバーして 自己負担ゼロ にしよう」
という制度改革を進めています。
実施目標は2026年度。
政府は保険適用による「費用の透明化・標準化」と「妊産婦の負担軽減」を狙っています。
【経済学から見た】出産費用無償化のメリット3つ
① 家計負担が減って出生率アップが期待できる
経済学では「費用=障壁」という考え方があります。
出産費用の自己負担がゼロになれば、「お金がかかるから出産は控えよう」という心理的・経済的障壁が減り、出生率アップの追い風になります。
② 所得格差や地域格差の解消
全国一律の保険適用により、地域ごとの「高すぎる病院・安すぎる病院」の差が縮小します。
結果として「低所得層・地方在住者」が不利にならず、所得再分配の効果が期待されます。
③ 長期的な経済成長への貢献
出生率アップは、将来的な労働力人口の増加につながります。
少子化による経済縮小リスクを軽減でき、持続的成長への布石になります。
【気をつけたい】経済学から見たデメリット3つ
① 財源はどこから?負担増の可能性
当然ですが「タダ」にするにはお金が必要。
政府は「支援金制度(企業・世代間で広く負担)」を検討していますが、
保険料アップ や 増税 という形で国民に跳ね返る可能性もあります。
② 地方の産科医院が経営困難に?
保険適用になると医療機関は「定められた料金」でしか請求できません。
これにより 小規模な産院や地方病院の経営が苦しくなり、
産科医療そのものが縮小する恐れがあります。
③ サービスの多様性が減るかも?
例えば「無痛分娩」「個室」「豪華な食事」などの付加サービス。
保険適用で「標準化」されると、これらは自己負担で別料金になるかもしれません。
妊産婦の多様なニーズに応えづらくなるリスクがあります。
【注目】地方自治体の先進事例|岐阜県恵那市
岐阜県恵那市では2025年度から、
市内出産なら自己負担ゼロ を実現する制度をスタート!
出産育児一時金を超える分は市が全額助成します。
「地方からの少子化対策モデル」として注目されています。
まとめ|制度設計と持続性がカギ
出産費用無償化は「家計支援」「出生率アップ」という明確なメリットがあります。
でも、「財源確保」「産科医療体制維持」などクリアすべき課題も少なくありません。
今後は
政府・自治体・医療現場・国民 が連携して、
持続可能で公平な制度設計 が求められます。
今後の動きも随時「自由.online」ブログでお伝えしていきます!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

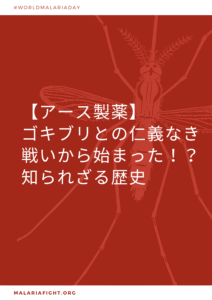
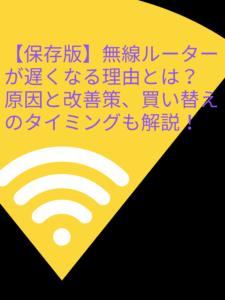
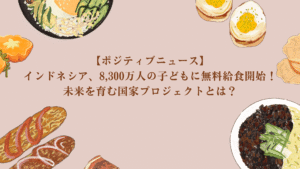
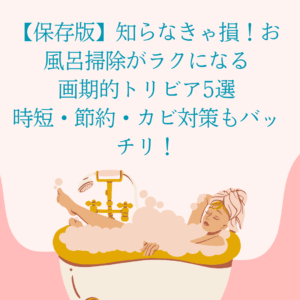
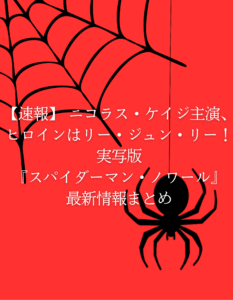
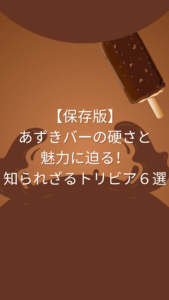
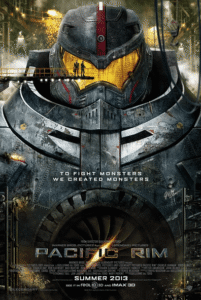
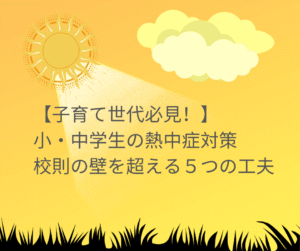
コメント